よくあるご質問
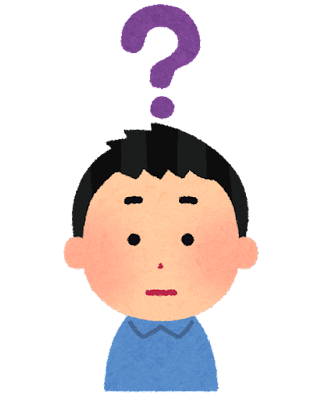
相続に関するよくあるご質問
はい。相続で必要な手続きをほぼすべて行います。
基本的に必要な相続関係書類の収集から遺産分割協議書の作成、不動産や預貯金、株式などの名義変更手続きのすべてを代行いたします。また、ご希望があればライフラインや不動産売却に関すること他、いろいろな手続きをお手伝いできます。遺産分割協議書と添付する全ての相続関係書類、相続手続きの知識がないと膨大な労力を使うことになります。特に不動産の名義変更登記には必須です。
いいえ。できません。不動産の相続では必須です。
それにプラスして、亡くなった方の財産の名義変更や解約には有効な遺言書がある場合を除き、故人の出生から死亡までの全ての戸籍・除籍・原戸籍謄本(亡くなっている人がいればその出生から死亡まですべて)や、相続人全員の戸籍謄本や住民票、印鑑証明書など関係書類が必要になります。
いいえ。窓口によっては必ずしも必要ではありません。
その代わりに、各銀行でそれぞれ所定の用紙に相続人全員の署名捺印が必須です。例えば、銀行窓口が5つある場合は最低(!)でも5回の署名捺印が必要になります。
当然ですが、上記の証明書もすべて提出しなくてはなりません。
はい。わかります。
当事務所では、銀行等の残高証明書をはじめ、名寄帳や登記簿謄本(全部事項証明)等の必要書類を収集し、相続財産の漏れがないように財産目録も作成いたします。
はい。伺います。
ご希望であればご自宅の他お好きな場所へ伺います。お仕事やデイサービス、通院などのご予定に合わせることも可能です。
遺言書であれば作成本番当日には公証人と証人2人が出張して行くことも可能です。
また、相続財産と家族構成をお伺いし、お客様の要望に沿った遺言書を作成サポートいたしますのでお気軽にお問い合わせください。
当事務所は相続・遺言専門で他の業務を受け付けない、遺言執行と相続手続きのプロフェッショナルです。
お客様それぞれの事案に合ったアドバイスをさせていただきますのでお気軽にお問い合わせください。









